|
|
|
|
更新日:2014年7月21日 |
|
|
|
|
| スピーカー自作、真夏の定番「STEREO誌付録スピーカーを作ろう」の季節となりました。今年は詳細内容が早くから公開されたので、私も5月から構想をスタートさせて、出来るところから製作を進めていました。昨日Amazonより書籍が届いたので仕上げを行い、無事完成しました。多分、世界で一番早い(?)製作記事と思います。 | |
| (STEREO誌2014年8月号が到着) | |
| (今年は豪快に2WAYスピーカーのセット、圧巻です) | |
| (しっかりとFOSTEXのロゴがあります) | |
| さて今年はスピーカーの図面がかなり早い段階から公開されていたので、事前の設計を進めることは容易でした。2年連続で雑誌のコンテストには落ちているので、今年はどうしようかなと考えています。もちろん私の場合、WEBで公開することに喜びを感じるのが優先されるので、今、最速でこの記事を書いています。今年の製作のコンセプトは「ラウンドフォルム」です。最近のオーディオ雑誌に載っている有名メーカーのスピーカーBOXは曲線を多用しています。私なりに曲線にこだわってみました。加えてBOX構造も平行対面が減るので、内部での反響には良い影響が出ると勝手に信じています。 | |
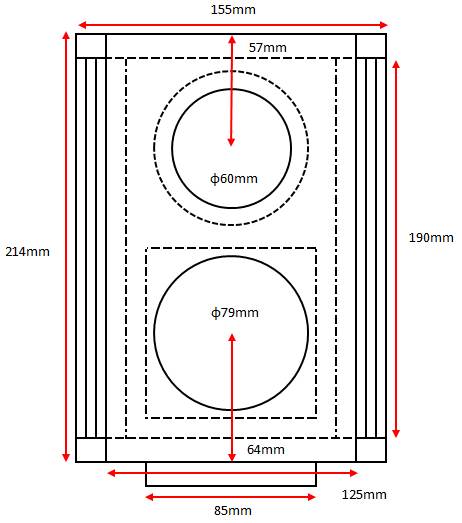 |
|
| (正面から見た図) | |
 |
|
| (背面から見た図) | |
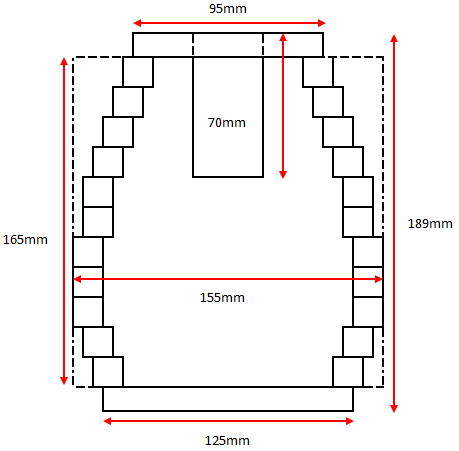 |
|
| (天面から見た図) | |
| 最初に完成した姿をお見せします。製作意欲が沸くと思います。 | |
| (完成後の雄姿、おお!!) | |
| 設計図からも判るように今回は背面バスレフタイプとしました。私の中での2WAYのスピーカーは上部がトゥイーター、下部がウーファーという配置になっていますが、STEREO誌での今回のスピーカーの使いこなしを読むと上側がウーファーで下側がトゥイータとするほうが良いとなっていました。そこで今回は少し工夫をして、どちら側でも設置出来るようにしました。もともとフロア型でのコンセプトですので、その影響です。デスクトップで使われる方には必要ないかもしれませんね。 | |
| 製作はフロア型にする部分から作ります。今まではその支柱部分を塩ビパイプで設計し、エンクロージャーの内部容量をかせぐこととしていましたが、今回はそれから決別して、単純な支柱とします。既製品を有効活用します。 | |
| (支柱の台座となる部分を作ります) | |
| 15mm厚のベニア板から200mm x 200mm を4枚切り出します。このあたりは自分でノコギリで加工が可能です。 | |
| (4隅をカットします) | |
| (更にカットして円形に近づけます) | |
| (木工用ボンドでしっかり、2枚張り合わせます) | |
| (それなりに、やすりでなめらかに) | |
| (つや消し黒で塗装します) | |
| (ウッドポールの丸座金φ80mmを使います) | |
| (重りに使う金属プレートも購入します) | |
| (台座の下に付けるスペーサーです) | |
| 日曜大工センターにあると思います。これら既製部品を使って支柱の製作を軽減します。 | |
| (上側に丸座金を取り付けます、万能ボンドと併用します) | |
| (底面には重りとなる金属プレートを取り付けます) | |
| (ウッドポールの支柱です。長さは皆さんの環境に合わせて下さい) | |
| (私の場合は683mmを選択) | |
| (塗装して完成です) | |
| 今回のエンクロージャーはベニア板と角材の混成です。いつもはひとつのエンクロージャーに6枚の板が必要でしたが、今回側面がラウンドするので、ベニア板は4枚しか使いません。板取りは12mm厚の900mm x 300mm のベニア板から2個分が取れます。(今回はあえて板取りは掲載しませんので、各自考えて下さいね。簡単です。) | |
| (天面と底面の板に角材の位置を記します) | |
| 天面と底面には12mm厚ベニア板を165mm x 155mmに切り出して使います。15mmの角材を5mmづつずらして配置するので、その下図を板に記します。ラウンドするので余分なベニア部分はカットしておきます。スピーカー本体と支柱はネジで固定しますので、そのナットを埋め込みます。 | |
| (M5サイズの埋め込みつめ付きナット) | |
| (ナットは必ず内側から埋め込みます) | |
| 天面と底面の両方に打ち込みますが、同じ取り付けにする必要があります。その上で打ち込む方向が異なりますので、充分注意して下さい。 | |
| (支柱とスピーカーの取り付けのつなぎ部分を作ります) | |
| つなぎ部分を作ります。12mm厚ベニアを85mm x 85mmにカットします。 | |
| (4隅を適当に切り取ります) | |
| コーナーをカットしてRを持たせます。このつなぎ部分に開けた穴が、スピーカーの天面と底面に開けた穴と同じ位置にくる必要があります。まずこのつなぎ部分を作ってから、スピーカー側の天面と底面に埋め込みナット用の穴を開けましょう。 | |
| (ウッドポールの丸座金φ63mm) | |
| こちら側の丸座金にはφ63mmを使います。先ほどの支柱に使ったものよりひとまわり小さいものです。 | |
| (塗装した後に取り付けます) | |
| 一応万能ボンドで固定しながらネジ止めします。このつなぎ部分は一旦ゴムを介してスピーカーに取り付けることにします。 | |
| (両面テープ付きのゴムシートです) | |
| (ネジを通す部分には穴を開けます) | |
| さていよいよスピーカーBOXの製作に取り掛かります。今回はラウンドフォルムにするので側面には角材を使用します。 | |
| (15mm角材を並べて使います) | |
| (正面のバッフル板です) | |
| 12mm厚ベニア板を214mm x 125mmにカットしてウーファー用にφ79mm、トゥイータ用にφ60mmの穴を開けます。 | |
| (背面板です) | |
| 12mm厚のベニア板を214mm x 95mmにカットしてバスレフ用にφ32mmの穴を開けます。 | |
| (バスレフポートの取り付け) | |
| VU25の塩ビパイプを70mmにカットして万能ボンドで取り付けます。 | |
| (正面、天面、底面を組み付け、側面の角材を順番に取り付けます) | |
| 15mmの角材を190mmにカットして順番に木工ボンドで取り付けていきます。地道な作業ですが慌てずにゆっくり組み立てて行きます。 | |
| (角材をずらす部分は5mmずつです) | |
| (もう一息で側面が完成)) | |
| ここまで来ると、角材間のボンドの厚みで最後の角材が入らなくなります。そこで少し厚みの薄い角材を買ってきて、当てることにします。 | |
| (12mm x 15mmの角材を購入) | |
| 私の場合丁度12mmが入りそうです。少しの加工は必要かもしれません。 | |
| (背面を取り付ける丁度の高さになりました) | |
| (背面を取り付けて一旦完成) | |
| 一応スピーカーBOXの原型が出来ました。まず最初に角材との隙間を埋めることが必要です。木工用ボンドでかなりふさがってはいますが、確実にしておきます。 | |
| (仕上がりも少しやわらかめのウッドシール材) | |
| (ウッドシールで隙間をふさぐ) | |
| 次に段差の大きい隙間をうめていきます。今回はエポキシの補修パテを使います。スピーカー2本を作るのに結構の本数を使いました。 | |
| (エポキシの補修パテ) | |
| (補修パテで隙間をうめて、ラウンドフォルムに近づけます) | |
| 最後には表面加工がしやすい、木工パテで補修します。 | |
| (木工補修用パテ) | |
| (段差のある表面を覆います) | |
| 以降、やすりがけ、再度木工パテを繰り返していきます。最初は#80,#120のやすりでみがいて、仕上げには#240を使います。 | |
| (ランドフォルムの完成) | |
| (背面には全体に木工パテを塗り込みます) | |
| バスレフポートの取り付け部を隠すために、背面には全体に薄く塗って対応します。やすりで磨いて滑らかにしましょう。これで塗装前まで完成しました。いよいよ塗装に入ります。 | |
| (つや消し黒で塗装しました) | |
| 表面が滑らかになるように塗装、やすりかけを繰り返します。やすりは#400以上が良いと思います。3回くらい繰り返せば良しとしましょう。 | |
| (底面に支柱とのつなぎを取り付けます) | |
| M5の長さ30mmのネジで取り付けをします。今回トゥイータが下側にくるようにしました。 | |
| (今回使わない反対側はM5の15mmネジで蓋をしておきます) | |
| (スピーカー端子の取り付け) | |
| 2WAYスピーカーですので、簡易的にもネットワークが必要です。今回は最も簡単な方法としてトゥイータ側にコンデンサを挿入することが推奨されています。そのような作業をスピーカー外部で行えるように端子はそれぞれ外側に出しておきます。後での変更が容易になります。この後スピーカーが到着するまで待ち状態となりました。約2週間程度このままでした。 | |
| スピーカーが到着した後、バッフル板にスムーズに入ることを確認して吸音材を入れます。私の場合は天面、底面、両側面にシート状のウレタン(?)を入れました。端子とスピーカーを配線してスピーカーを取り付けます。 | |
| (トゥイータ側のダンパ) | |
| トゥイータはバッフル板の穴径に対してどこで位置決めして良いのかわかりにくいので、スピーカーに添付されているダンパが穴あけ位置の役に立ちます。 | |
| 片や、ウーファー側に付いているダンパは使い勝手が良くありません。最初ダンパ無しで取り付けていたのですが、特定の周波数でフレームが鳴くことが判明し、ダンパを手作りしました。 | |
| (1mm厚のブチルゴムシート) | |
| (ウーファー用スピーカーのダンパになるように加工します) | |
| ここまででついにスピーカーの完成です。支柱に取り付けてみましょう。 | |
| (大変スリムなスタイルですね) | |
| (ラウンドフォルムが非常に高級感を醸し出しています) | |
| いよいよ音出しに入りますがその前に、トゥイータに取り付けるコンデンサを準備します。 | |
| (ASC製の1uFのコンデンサです) | |
| メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサとしてオーディオに定評のある(多分)ASC製1uF400Vを使います。千石さんでネット購入しました。それなりの価格なので付録についているものと比較にはなりません。結構良い音がしています。 | |
| (トゥイータは逆接続します) | |
| 雑誌の記載にもありますようにトゥイータは逆接続して使います。上図のようにすればOKです。それでは私のオーディオ環境につないで特性を取りましょう。 過去のスピーカーの特性はここを見て下さい。 自作スピーカーの周波数特性を測定する(その2) |
|
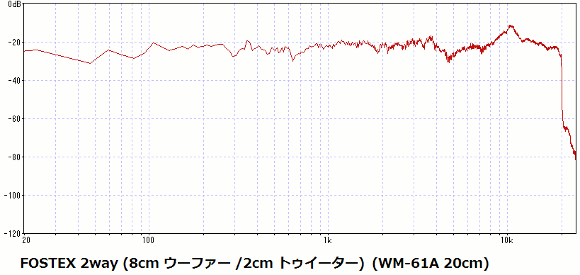 |
|
| 雑誌にも記載がありますが10kHz付近でピークがあるスピーカーとのことですのでその影響が少し出ています。この特性はウーファーとトゥイータの間くらいにマイクを置いて取りました。結構良い特性が出ていますね。低音も結構出ています。私の好きな低音です。さすがに2WAYですので綺麗な高音も聞きやすいです。音像の定位がしっかりしているという印象です。背面バスレフの影響なのかもしれませんが、他スピーカーで見られた100Hz〜200Hz間のディップが全くありません。大変良く出来ました。 | |
| 今回のラウンドフォルムは大正解でしたね。作製の工数は多くなりましたが、手間をかけた分仕上がりには大満足です。まだまだスピーカー製作はやめられませんね。しかし来年はどんな付録になるのでしょうか。 | |
|
|
|
|
オーディオクラフト工房へ戻る |
|
|
|
|
|
|