|
|
|
|
更新日:2015年4月9日 |
|
|
|
|
| 最近のスピーカー製作ではまっているが「ラウンドフォルム」と「フロア一体型」です。何度もエンクロージャーを作り直してきたスピーカー達ですが、またまた作り直します。今度はStereo誌2012年8月号のScanspeak製10cmフルレンジがその餌食になりました。私のオーディオシステム環境では4台のスピーカーを切換えて駆動出来るのですが、その内2台が「フロア一体型」になったことになります。低音が充実している中で、ボーカルが聞きやすく、とても良いシステムに仕上がりました。 | |
| (かなりの懐かしさを感じるScanspeak製10cmフルレンジ) | |
| (当時かなり盛り上がった本物のしるし) | |
| 前回の製作でScanspeak製5cmフルレンジを作り直しましたが、結構低音がしっかりしたので、今回も同じ方式で設計しました。全高900mm超えで、背面バスレフです。バスレフポートはセンターに配置しています。 | |
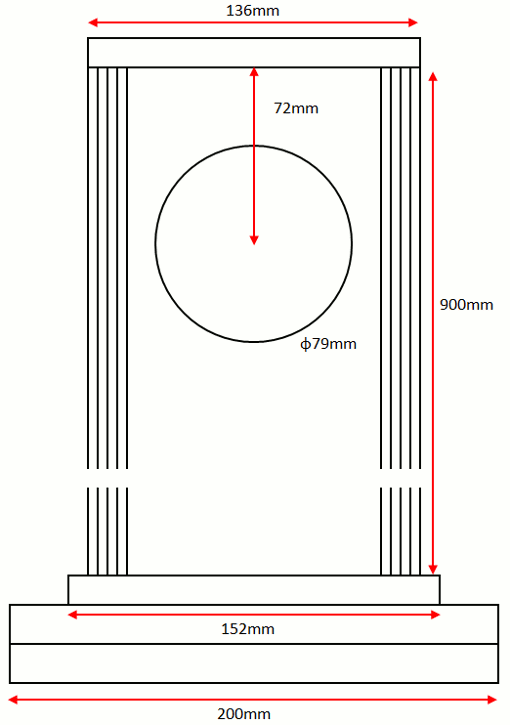 |
|
| (正面から見た図) | |
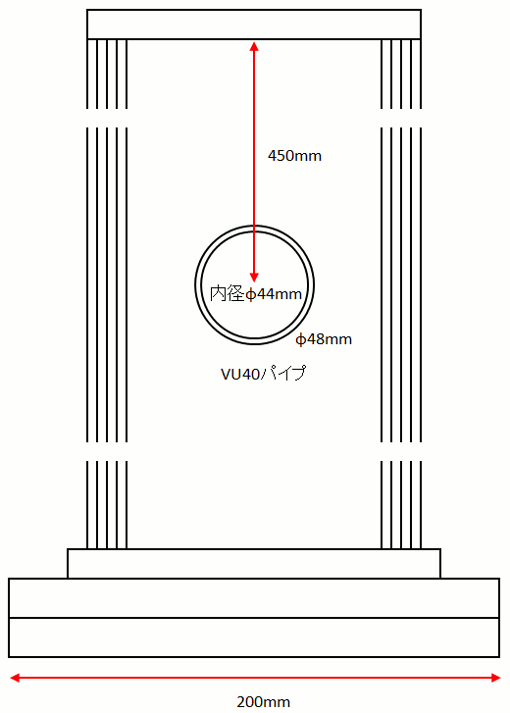 |
|
| (背面から見た図) | |
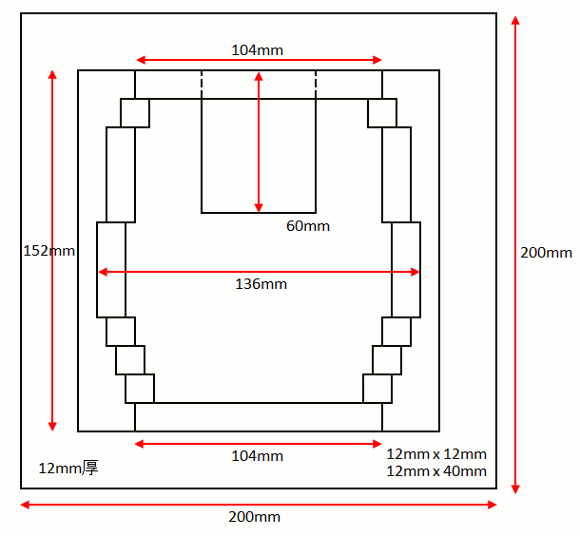 |
|
| (天面から見た図) | |
| 各段差は4mmの設計ですが、背面付近については6mmの部分が2箇所ありますので、製作の際は注意して下さい。 | |
| どんな完成形になるか見ておきましょう。 | |
| (とれもしっかりとしたフォルムですね) | |
| ラウンドフォルムに対してその段差を今回からパテで埋めることはやめました。全高があるのでパテの量がはんぱではありません。小遣いがいくらあっても追いつきませんので、正確には段差のあるラウンドフォルムとなっています。ベース部の大きさは200mmx200mmにしています。この大きさにうまく乗せることが出来るようなエンクロージャーとしています。ベースの大きさを統一することで、後で作り直しても設置場所に困ることはありません。今までは合板と12mm角のヒノキ材で構成していましたが、今回初めて40mm幅のヒノキ材も使用します。合板の大きさを小さくは出来ますがトータルコストはかえって高くなるようです。ヒノキ材は合板より軽いので重さを稼ぐには少し不利だったかもしれません。 | |
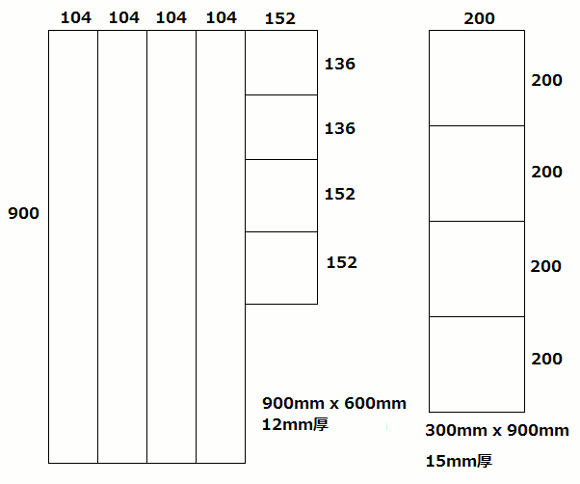 |
|
| (合板の寸法図) | |
| エンクロージャー部は12mm厚合板、ベース部は15mm厚合板、ヒノキ材は12mm厚で40mm幅と12mm角材を使用します。 | |
| (エンクロージャー用合板の切り出し) | |
| (スピーカーとバスレフ穴をあける) | |
| (バスレフダクト長は60mmとした) | |
| (バスレフポートは万能ボンドでしっかりと接着) | |
| (天板に板の取り付け位置を書き込みます) | |
| (余計な部分をカットします) | |
| (底面板にも取り付け位置を書き込みます) | |
| (12mm角のヒノキ材) | |
| (12mm厚40mm幅のヒノキ材) | |
| これらの材料を用いて組み立てていきます。 | |
| (積み上げ方式で隙間の無いように接着しましょう) | |
| (吸音材を内部に貼り付け) | |
| (バスレフポート周辺にも吸音材を貼り付け) | |
| 今回はエンクロージャーとなる前に吸音材を内部に貼り付けます。吸音材にはクッション用の素材(キルトシン)を使いました。私は手芸屋で購入しています。 | |
| (ちょっと太めのエンクロージャーになりました) | |
| (背面のバスレフポートはこんな感じに) | |
| (細めの角材を準備) | |
| 正面と背面部分のみラウンドフォルムに段差がわかりやすいように見えたので細めの角材で段差を埋めることにしました。 | |
| (正面のすぐ横に細めの角材を追加) | |
| (背面も同様に追加) | |
| ベースは過去の製作を流用しました。というより合板を買って切り出すのが少し面倒だったからです。過去に作り直したものから塩ビパイプを取り外し(というより切り取って)、ひっくり返して使います。ということで2枚重ねしていたベースには全厚みの半分まで穴が開いていることになります。またスピーカーを倒れにくくするために、より一層ベースの重さを増すことが必要になります。 | |
| (重さを稼ぐために使う座金) | |
| ホームセンターを物色していたところ結構な厚みのある座金を見つけました。これをベースに複数貼り付けることで重さを増すことにします。 | |
| (12枚の座金を貼り付けます) | |
| 座金の厚み分以上のゴム足を取り付けてベースの完成です。更に前回と同様にスピーカー下部に重心をもっていくために、板状の重りが必要です。ホームセンターにあるラック自作をする鉄板を今回も使います。 | |
| (重りに使う鉄板です) | |
| これらを接着して、こうなりました。 | |
| (エンクロージャーとベースを合体してサイドに鉄板を貼り付け) | |
| サイドの鉄板貼り付け前には必ず紙やすりで下ごしらえをしておいて下さい。#120、#240の順で磨いておきましょう。コーナーの角にRがつく感じで。 | |
| (つや消し黒で塗装してエンクロージャーの完成) | |
| 塗装は最低でも2回は必要です。塗装ごとに必ず#400の紙やすりで表面をなめらかにしましょう。そうすることで仕上がりがつるつるの手触りになります。 | |
| (加工したブチルゴムシート) | |
| 過去の経験からスピーカーを直接エンクロージャーに取り付けると、どこかの周波数で必ずスピーカーが鳴きます。それを防ぐために1mm厚のブチルゴムシートを挟みます。特に今回ネジ穴をポンチで開けましたので、スピーカー取り付けのネジ締め時にシートがゆがむことがなくなり仕上がりがとても良くなりました。 | |
| (完成した雄姿) | |
| (スピーカー周辺も良好な仕上がり) | |
| とてもどっしりとした感じを受けます。これも良い低音が期待出来ますね。 | |
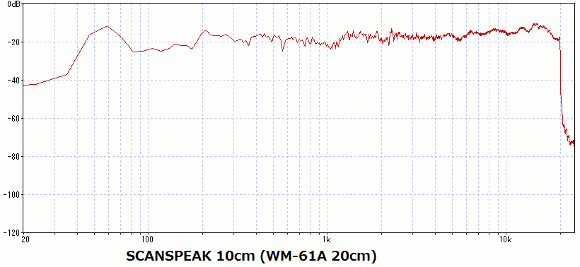 |
|
| (低音バリバリで高音までかなりフラットな特性) | |
| バスレフポートの設計通りの低音が増強されています。かなりの高音まで伸びていますので、今回も大成功といったところでしょうか。低音部の特性に各人の好みがあるとは思いますが、私は好きです。ドンドンと響くのが。箱が変われば音も変わる。さて次回は何が飛び出すのでしょうか。まだまだオーディオネタは続きます。 | |
|
|
|
|
オーディオクラフト工房へ戻る |
|
|
|
|
|
|